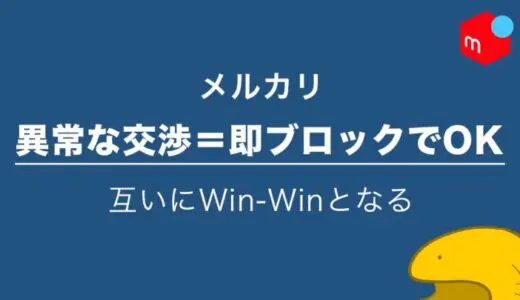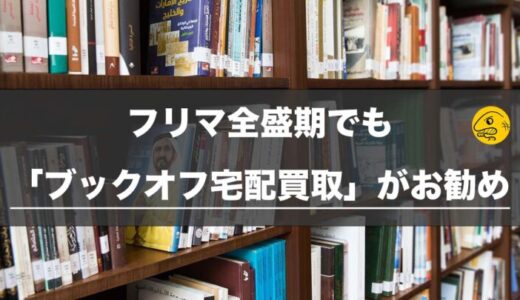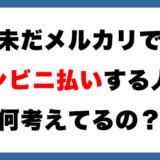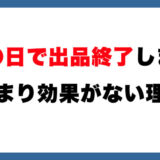〈景品表示法に基づく表記〉当サイトはアフィリエイトプログラムによる広告収益を得ています。
先日、大阪万博にて開催された「サーキュラーエコノミー研究所」に行ってきた。なんと経済産業省が開催する力の入れようで、循環経済(サーキュラーエコノミー)について楽しく学ぶことができた。
まず簡単に循環経済について解説する。これは資源の効率的・循環的な利用を目指しながらも、無理のない市場活動を続けていく経済のこと。例えば「未来の地球のために今すぐプラスチックを廃止します!」じゃ環境によくても経済的に人類が終わるので、使うにしても廃棄物が出にくい仕組みや再利用を意識しましょう、ってこと。
この循環社会、私が学校で習った時よりもビジョンが具体的になっている。例えば環境を考える言葉として『3R』を聞いたことがあるだろう。それぞれ
- Reduce(減らす)
- Reuse(再利用する)
- Recycle(再資源化する)
の頭文字で構成される。しかしこの思考はゴミが発生することを前提とした考えであり、これからの地球環境を考慮すると更に一歩先、ゴミを生み出さないことが大切になる。
そこで新しく提唱されているのが『5R』だ。先ほどの3つに加え
- Refuse(不要なモノを買わない・貰わない)
- Repair(壊れたモノを修理して使う)
この2つの考えを取り入れたものである。
これを踏まえて循環経済を表現してみよう。目の前に人形があるとしよう。この人形は再生プラスチックで作成されていて資源を無駄なく使っている。また壊れたとしても手直ししやすい設計がなされている。
もし仮に人形がいらなくなっても、フリマアプリを通じて必要とする人に譲ることも、寄付することもできる。捨ててしまっても材料ごとに分けることでリサイクルされ、また新しい人形の素材として使うことができる。

具体例を挙げると、ハッピーセットのおもちゃが有名だろう。マクドナルド各店舗におもちゃ回収ボックスが設置されており、イートイン時に使うトレイの材料などにリサイクルされている。またユニクロにも自社製品を積極的に回収し、災害支援として服をリユースしたり、燃料として活用している。
従来のように製品作りっぱなしで後は各自処分してください!ではなく、循環経済に組み込めるように生産活動をすることが求められていくのだろう。そして消費者の私たちも『5R』を意識した生活が大切になってくる。スーパーで紙パックをリサイクルするとか、ペットボトルはフィルムを剥がして、キャップを取って捨てるとか。
そう聞いて、ふと気になった。何故ペットボトルとキャップは異なる素材なのだろうか。どちらも同じPETにすればリサイクルが捗るのではないか?捨てる時もメンドウじゃないし。
いろいろ調べた結果を簡単に言うと、キャップが柔らかい素材になることで密閉性が高くなり、また開閉しやすくなるようだ。なるほど、リサイクルしやすさを優先して本来の目的を果たせなきゃ意味がないって訳だ。

そしてもう一つ。ペットボトルのゴミ箱には、キャップと本体の投入口が分かれているものがある。しかし中のゴミ袋は同じで結局同じところに捨てられる。なら、そのまま入れても変わらないんじゃないか?
これも解決した。ペットボトルキャップと本体は素材が違うため、水槽に沈めるとキャップだけ上に浮かぶのだ。そのため同じ袋に捨てられても水槽に入れると簡単に分離できるって理屈。
ちなみに本体に付いているキャップのリング部分、これは多少混ざっていても、リサイクル製品の品質にほとんど影響しないため取らなくて良いらしい。取るのがめんどくさかったので朗報だ。
また非常に興味深い話も聞けた。ペットボトルを捨てるときに潰すべき理由。これは物理的にゴミ収集車に入る量を増やすためでもあるのだ。ペシャンコなら沢山入るが、潰れてないと嵩張るし、プレスした際に破片が飛び散ることで二次被害も発生するようだ。
これらのことを学ぶうちに、いくらAIが発達したところで、この作業は代替できないんだろうなと思った。「全自動ペットボトル洗浄してキャップ外す君」を作ったり設置する費用を考えると、私たちが捨てるときにフィルムを剥がし、軽くすすいでキャップを外す方が簡単である。
万博で数少ない「予約なしで入れる展示」だから期待していなかったが、思いのほか生活に役立つ学びを得られた。ぶっちゃけキャップを外すのが面倒でそのまま捨ててたけど、今後はしっかり外しておこうと思う。
ちなみに来場者に配布された漫画冊子は早速フリマアプリで出品されていた。どうやら学びを実践しているようだ。